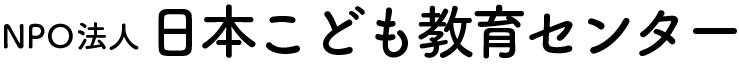2022.03.19
幼児教育に知育を取り入れる理由とは?遊びとの違いもご紹介
目次
幼児教育に知育を取り入れる理由とは?遊びとの違いもご紹介

幼児教育の中には、「知育」というものが必ず含まれています。
ただ、「知育」という言葉は聞き覚えがあっても、その意味について明確に知っているという方は少ないのではないでしょうか?
本記事では幼児教育に知育を取り入れる理由と、「遊び」との違いについてもご紹介していきます。
そもそも「知育」とは?

知育とは、イギリスの学者「ハーバート・スペンサー」が提唱した「三育」と呼ばれる3分野に分かれた教育のうちの1つです。
三育の考え方では、「知育・徳育・体育」の3つの分野をバランス良く行うことによって、一人一人の子どもが持つ能力・実現力・生きる力が育まれていくと考えられています。
三育における知育は思考力や判断力などの、「知力・知能」を伸ばすことを目的とした教育です。
知育の教育を通じて、子どもに行動力や情報処理能力を身に付けさせることができるのです。
「知育」と「遊び」はどう違う?

知育を通じて知力や知能を伸ばすとは言っても、机に向かって詰め込んで学習を行うというものではありません。
幼少期の知育では、「子ども自身が楽しみながら自然に学べること」を重要視しているので、私たち大人の目線から見ると「遊んでいるようにしか見えない」ということもあるでしょう。
しかし、「知育」と「遊び」は異なるものです。
知育の活動では、子ども自身の「やってみたい」という気持ちを大切にし、目の前の問題や課題に対して試行錯誤を重ね、「できた!」という達成感を得ることに重視しています。
よく考えて行動すること、達成感・成功体験といった経験は日常生活の中でも得ることができます。
しかし「遊び」は特に何かの目的をもたないことに対して、「知育」では子どもの年齢に適した課題・問題を設定して「一人一人の子どもの能力を育てる」という目的をもって行います。
このことから「知育」と「遊び」の明確な違いとして、「自分で考える力を養う」という目的を明確にもっているかどうか、ということが大きな違いであると言えるでしょう。
幼児教育に知育を取り入れる理由

幼児教育に知育を取り入れる理由をいくつかご紹介します。
幼児期の脳は柔軟性に優れているため
3歳くらいまでの脳は吸収力が非常に高いとされており、柔軟性にも優れています。
幼児は外からのさまざまな刺激を受けてたくさんのことを学び、「自身の生きる方法」を模索していきます。
脳科学の研究では、おおよそ3歳くらいまでは右脳が働き、3歳を過ぎると左脳の方が活発に働くとも言われています。
そのため、3歳頃までは右脳を上手く刺激するような知育を行うことが良いとされているのです。
右脳が育つことによって記憶力・想像力に優れるほか、感情表現も豊かに育つとされています。
地頭の良さを育てられるため
頭の回転が速い・物事を論理的に考えることができるといった大人になれれば、仕事に関してだけでなく、生きていくことにおいてその能力をさまざまな場面で発揮することができます。
知育を幼少期に行っておくことで、こういった地頭の良さも育てることができるのです。
幼児期にIQを伸ばすことができるため
IQは「知能指数」のことを指します。 これは学力とは異なり、記憶力・考える力といったものを計測できる指数です。
IQを伸ばすことで、自立心・ほかの人に対する思いやりの心も高めることができるとされています。
とくに幼少期は脳が柔軟であるため、知育を行うことでこのIQをグッと伸ばすことができるのです。
おわりに
本記事では幼児教育に知育を取り入れる理由と、「遊び」との違いについてもご紹介しました。
「遊び」はとくに明確な目的や意味を持たないのに対し、知育は「自分で考えて行動する」というはっきりとした目的を持って行われます。
子ども一人一人の「生きる力」を伸ばしていくことが、「知育」において最も重要なポイントなのです。
日本こども教育センターでは、「知育」に関する講師養成講座を開講しています
日本こども教育センターでは、0~1歳対象の「さくらベビー知育インストラクター講座」と2歳~5歳対象の「知育インストラクター養成講座」の2つの講座を開講しています。
どちらの講座も、DVDで受講できるものなので、お家でお仕事や家事の合間に、ご自分のペースで学ぶことが可能です。
0~1歳対象の「さくらベビー知育インストラクター講座」
赤ちゃんを対象とした内容で、フラッシュカードの見せ方や100円ショップで揃えられる教具のご紹介など、盛沢山な内容です。
ママが見ても、日々の遊びに役立てられる内容で楽しいと思います。
2~5歳対象の「知育インストラクター養成講座」
2歳以降のお子様を対象とした知育インストラクター養成講座は、
・なぜ早期教育が必要なのか
・2~5歳のそれぞれ学年毎の模擬知育レッスン
・モンテッソーリ
などの内容盛りだくさんです。
これから知育教室をはじめたい、ピアノやリトミックのレッスンにちょっと取り入れたい方にピッタリの内容です。
ご自分のお子様に役立てたい、幼稚園や保育園にとりいれたい、リトミックやベビーマッサージ、ピアノや英会話のレッスンに少し入れてみたい、など毎回様々な目的をもった方が受講してくださいます。
知育インストラクター養成講座を受講された方の感想
初めて日本こども教育センターのリトミックを見学させていただいた時のことは今でも鮮明に覚えています。
内容の豊富さ・楽しさ・流れるような展開などに時間を忘れてしまいました。
以前より自宅教室でプライベートレッスンの形でリトミックレッスンをしており、グループレッスンも始める予定で準備をしていた時期でもありましたので受講を決めました。
受講をしてとても印象深かったことがあります。
それは、受講者同士があっという間に打ち解けその後も繋がりを持たせていただいていること、学びの場なのに楽しすぎるほどの時間だったことです。受講内容はもちろん素晴らしいものでした。
その後も、ベビー知育インストラクター・知育インストラクター・ベビーマッサージの講座を受講し、色々な資格を取得しました。
特に知育は、幅広い年齢に対応しており、リトミックレッスンには、0歳さんから知育も取り入れ、お母様方にご好評をいただいております。
「0歳のベビーちゃんにどんなことが出来るのかしら?」と思われるお母様も多いと思います。
ベビーちゃんは、初めて見る教材や楽器を不思議そうに眺め、次はちょっと触ってみますよ。
こうして新しい経験が始まります。
つまんだり引っぱったりにぎったり・・・感覚を育んでいきます。
頭の中はフル回転ですね。
1回のレッスンの中だけでも出来ることが増え、お母様には嬉しい驚きだそうです。
知育講座の教材のピクチャーカードや身の回りにある物(紙やリボンなど)を使うレッスンは、「毎日お家での遊びが同じようなことばかりで飽きてしまうので、お家にかえってからもまねをして遊べて楽しいです!」とお母様から伺っています。
「シニアのリトミックとボイストレーニング教室」では、リトミックをどんどん取り入れており、シニアの皆様にとても喜んでいただいております。
また、私のピアノレッスンの導入には、リトミックや知育が欠かせないものとなっております。
他業種の先生方とのコラボレッスンや保育園でのリトミックなど、活動の場もとても広がりました。
日本こども教育センターの講座は、内容がとても豊富で具体的・実践的だと思います。
受講後すぐから、又は自分なりにアレンジしながら、レッスンに活かせますので、自信を持って講師のお仕事を続けられます。
日本こども教育センター 知育インストラクター講師養成講座はこちらから
関連記事
-
2021.11.18
発達支援のプロフェッショナルとして子どもに合わせた支援をしよう!
発達支援のプロフェッショナルとして子どもに合わせた支援を...etc
-
2021.11.17
生きる力を育てる知育 自分で考える力や積極的に...etc
-
2021.11.08
リトミック講師になるためには?どのような資格が必要? ...etc